
公共下水道接続工事です。
各市町村には下水道が完備されている下水道区域がございます。
くわしくは各市町村の下水道課へお問い合わせください。
さて、今回は新築のお宅の宅内下水道配管工事です。
下水道の桝(お掃除点検などの目的のため)は基本的に管の起点、屈曲点、接合点、管径の100倍を超えない部分へ据え付けることとなっています。
一般の宅内の下水道工事の場合、通常下水本管の径はφ100mm、起点の深さは200mmほどです。
起点から下流にある公共下水道接続ますまで勾配をつけて自然落差で汚水をスムースに流れるように配管してあげます。
この際の勾配は管1mに対し、2cmが基本の我々の言葉で20パーミル(‰)と言っています。
1/50、1/100などという呼び方もありますが、建物内部などで使われます。
1/50と20パーミル(‰)は呼び方は違えど意味は一緒です。
(パソコンなどをお持ちの方、ぱーみる を変換してみてください ‰ ←出ますか?)
これ以上でも以下でも汚物を管内に置いてきてしまったりする場合がありますので、注意して設計、施工をいたします。

写真左は建物より接続する桝へのショットです。
こちらのお宅では軟弱地盤の為、地盤の浮き沈みが想定できますので、
伸縮可とう性のすぐれた埋設用エバフレキジョイントで接続施工しています。
一般的には使用しません。

さて、各接合点に設けた枡を経て、これより下水道の本線は90度に曲がり公共下水道の接続ますまで一直線です。
勾配は先ほどいった20‰です。
ビニール管は日当に置くと夏場などは弓なりに熱で変形してしまいます。
埋め戻しの際には逆勾配になったりしないよう、上流側から勾配を見ながら管下端に隙間のできないよう、しっかりと埋め戻し、浮き上がりの無い様に埋め戻します。

左写真は掘削完了後、床均しをしている写真です。
管のまっすぐを確認するため水糸を張って通りを見ます。
あと、書き忘れましたが、寒冷地では凍結深度が設定されていて、それより深く施工しなければならないことがあります。深いと施工もそれなりに大変です。
これより公共下水道接続ますまで配管しそれに接続します。
桝への接続には、最近の下水道では接続ますもビニール製のφ200mmの小口径ますが一般的となってきています 。
こちらへに接続は受け口ホールソー接続となっています。写真はちょっとないので説明も次回にいたします。
接続が完了したら、各市町村の下水道課へ装置完成届を提出いたします。
提出するとおおむね1週間以内に担当部課から検査の日程をお知らせがあります。(自身で日程を決める市町村もあります)
提出した設計書どおりに配管されてるか、スムースに水が流れ、水の溜まりはないかなどを立会で検査します。
検査完了しますと、下水道の利用開始となり、下水道料金が発生します。

今回の工事は浄化槽(合併処理浄化槽)7人槽を撤去し、下水道への接続工事となります。
道路に面した駐車場への施工となりますので、いままで使っていた浄化槽は綺麗に引き抜き、埋め戻しとなります。
なお、カメラの不具合で写真が少ないですが、説明文で渇愛とさせていただきます。
では、説明します。
上の写真では浄化槽周り、新設配管部分のコンクリートをカッターで切断し、ブレーカーで取り壊しを行った後、掘削している写真です。コンクリートが思ったよりぶ厚く打ってあって、おまけに鉄筋やら補強筋やらで解体に時間がかかり、手間を取りました。

掘りあがりました。
既存の浄化槽は7人槽で巾約1m長さ約2.5m深さが約1.6mくらいあってほぼ深さを1mくらい掘らないと引き抜いて持ち上げることは不可能です。
今回の現場は駐車場ということもあって、重機が入りましたのでそれが可能となります。

既存の浄化槽を持ち上げている写真です。
結構でかいです。中身が入っていたら絶対持ち上がりません。中身は清掃業者さんに引き抜いていただいて、清掃も完了しています。当たり前ですが。
やはり持ち上げるときに引っかけたりいろいろしますので、これを別の現場で再利用というわけにはちょっと行きません。これは廃棄処分です。
まだそんなに使っていないのでもったいない気もしますが、下水道化にしたら利用価値はほぼありません。
しかし、これを防火水槽や庭巻きの水を貯水しておくために雨水を引き込み利用するということも可能で、市町村によっては補助金も交付される地域もあるようです。

きれいに浄化槽の引き抜きが完了しましたら、再生の砕石を投入します。完全に引き抜くとこれが2tダンプ2台は余裕で入ってしまいます。
20cmほど埋めたらプレートで転圧し、また20cm埋めたら転圧を繰り返し、最後に水で締めます。

転圧をしっかりしながら新設の下水道管の配管もします。
転圧がしっかりしていないと、新設の配管がたみが生じて汚物が溜まるなどの現象が起きますので念入りにします。
既存であった浄化槽の放流側には キャップをして雨水などが侵入しないように処置をします。
下水道の接続ますはφ200となっていますので、200×100の受け口ホールソーという部材を使い、接続ます立ち上がり部にφ120の穴あけをし、加工します。
写真はありませんがそうして配管した下水道管の周りをさらに転圧し、埋め戻します。
あとは、鉄筋を並べ、コンクリートを打設したら工事完了です。
仕上がりの写真はありません。
なぜかというとカメラ内のメモリーカードが破損したからです。
というか仕事用に使っているカメラが未だにスマートメディアだったのです。
この工事後、カメラを新調しました。
オリンパスの防水防塵カメラです。いまどきのSDカードです。
SDカードXCまで対応です。 ただし画素数が多すぎなんですよね・・・
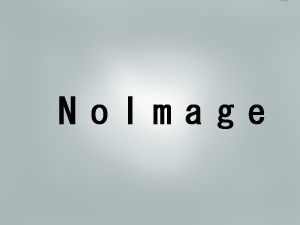
ーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーNoTextーーーーーーーーーーーー


